JMPマガジン31
EBMによる糖尿病経口薬の選択と適正使用-糖尿病コントロールのために
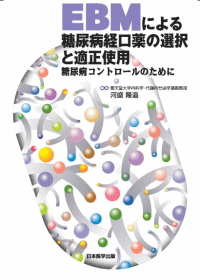
大規模市販後調査、大規模研究などのエビデンスをもとに具体的に症例提示をしながら糖尿病経口薬の選択と適正使用を解説。
第Ⅲ、Ⅳ章では≪どういうふうに治療したか≫≪なぜこういう治療をするか≫EBMに基づく文献の提示など、糖尿病経口薬治療の実際を実践的に解説
糖尿病診療に携わる医師、糖尿病療養指導士、薬剤師、看護師、栄養士などの医療スタッフに。
序文
2型糖尿病ほど甘く捉えられている疾病はない,2型糖尿病ほど健康寿命を短くしている危険因子は他にない,と常々考えさせられる。
症状の全くない2型糖尿病を何故,緻密に診ていかなければいけないのか?いうまでもなく,網膜症,腎症,神経障害という糖尿病特有の細小血管障害の発症・進展を抑制することにある。そのため,血糖コントロールが重要であることは言を俟たない。しかし,今日の糖尿病治療においては,同時に動脈硬化の発症・進展をも防止しなければならない。そのため,体重,血圧,脂質,など総合的にコントロールすることが必須となる。
血糖コントロールに関しては,朝食前空時血糖値をできうるかぎり正常域に近似したレベルに維持することが求められる。加えて,食後の異常な血糖値上昇すら抑制する必要があることもEBMとして示されるにいたった。
血糖値は全身の“糖のながれ”の結果である。2型糖尿病は一例一例で,その時々で病態整理が異なる。一適の血液,尿から“糖のながれ”を推測していかなければならない。
2型糖尿病の本態は,インスリン分泌の量的,分泌パターン的異常に,全身臓器におけるインスリンの動きの低下が加味された状況である。種々の経口糖尿病薬が,乱れた“糖のながれ”のどの点に作用して,“糖のながれ”を是正しているのか認識するべきであろう。
本書では,刻々と変動する,多彩な2型糖尿病の病態をその時々で的確に把握し,最適の治療法を実践する上でのヒントをEBMから論じてみた。いまや,種々の治療手段を手にしていることを実感していただきたい。
執筆してくれた若い医局員などのため,ご批判をいただければ幸いである。
2007年4月吉日
順天堂大学医学部内科学
河盛隆造
◆目次◆
- Ⅰ 糖尿病の新しい診断基準・ガイドライン
- 1 糖尿病の新しい診断基準
- 2 糖尿病の新しい治療ガイドライン
- Ⅱ 糖尿病経口薬-選択と適正使用のための基礎知識
- 1 α-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI)
- 2 メトホルミン
- 3 スルホニル尿素薬(SU薬)
- 4 グリニド系速攻型インスリン分泌促進薬
- 5 インスリン抵抗性改善薬
- 6 その他の治療薬情報
- Ⅲ 糖尿病治療の実際
- 1 IGT患者への薬物介入
- 2 食後高血糖(注目される軽症2型糖尿病)の治療-α-グルコシダーゼ阻害薬とグリニド系薬の使い分け
- 3 肥満患者の治療
- 4 高脂血症を合併した2型糖尿病-高脂血症治療薬を含めて
- 5 高血圧を合併した2型糖尿病-高血圧治療を含めて
- 6 進行した動脈硬化症合併2型糖尿病
- 7 高脂血症と高血圧を合併した2型糖尿病(軽症)
- 8 高齢者糖尿病
- 9 小児・若年期2型糖尿病
- 10 腎症合併例
- 11 末梢神経障害高度例
- 12 インスリン療法中の患者へのα-グルコシダーゼ阻害薬併用法
- 13 インスリン療法中の患者への経口薬の併用法(メトホルミン,スルホニル尿素薬)
- Ⅳ 糖尿病経口薬自由自在-こんなときどうする?
- 1 シックデイのとき
- 2 認知症患者への投薬法
- 3 ステロイド糖尿病(インスリンを使う前に)
- 4 服薬コンプライアンスをあげるために工夫すること
- 5 患者への薬の効能と副作用の説明
- 6 治療のゴールをどこにおくか?年齢や合併症の状況に合わせた管理目標の設定
- 7 薬の効果を判定するまでに必要な期間は?切り替え時と併用時
- 8 いつインスリンに切り替えるべきか?経口薬の二次無効とは?-ゴールが達成できないとき
- 索引